ps3 ダウングレード 4.11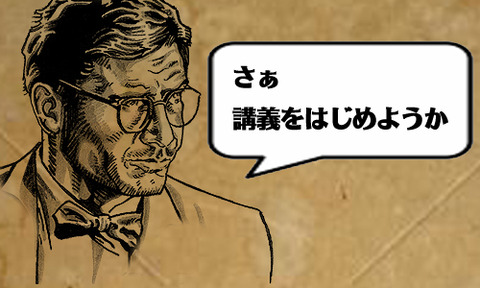
何人かの方からもらった質問の、その回答みたいなものです。
「ジョーンズ博士はどうやって記事を書いているんですか?」というような質問をよくいただきます。実はそんなに難しいことはまったく考えておらず、思ったことをただ書いているだけなのですが(笑)、そういう返し方も失礼かと思ったのでそれっぽいことを書いてみたいと思います。
こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。
今回は、私がこのブログに記事を書く際の「手順」と「気をつけていること」を書き連ねてみたいと思います。あまり何かの参考にはならないと思うので、それなりの心持ちで読んでくださいね。
 まず、ゲームをプレイします。
まず、ゲームをプレイします。

「記事を書こう」と思ったゲームをプレイします。基本的に、クリアするまでプレイするのがデフォルト。内容がクソ長いものに関しては20~30時間で区切りをつける場合もありますが、ひとつの作品をある程度しゃぶりつくさずに意見を述べるのはフェアではないと思っているので頑張ります。
でも私の場合、本業が忙しいため、なかなかゲームをやる時間が取れません。「ゲームは1日1時間」という高橋名人の言葉を守り、なんとか1日1時間はやるように心がけている感じです。
 クリアした際に心に湧いたものを、箇条書きにします。
クリアした際に心に湧いたものを、箇条書きにします。

ネット上で書かれているそのゲームの評判はほとんど気にしません。レビューとはプレーヤーの感想文でしかないので、「その人はそう思っただけ。でも俺は違うかもしれない」が基本のスタンスです。箇条書きは大体こんな感じの内容を書いていきます。
?つまり、このゲームはどんなゲームだったのか?
?どこにグッと来たか?
?↑なぜ、グッと来たと考えられるか?
?このゲームをやって何を考えたか?
?プレイ前とプレイ後に違和感はあるか?
 記事にする際に気をつけていること。
記事にする際に気をつけていること。

できるなら「面白い!」と感じてもらえる記事を書きたいと思っていますが、特に狙っていることはありません。ただ、「読み手が自分でも思いつく」、「新鮮味の感じられない内容」、「内容が簡素すぎて読み応えがない」ものは、個人的に興味を持てない記事なので、そういうのは避けたいですね。
ここで大事になってくるのが、一般的なこのゲームの評価はどうなのか?という視点。一部のマニアだけでなく、一般的な評価を踏まえて、それに対して自分はこう思う…という論調は意識していますね。この書き方にしないと、読み手のことを無視した、ただの俺的ゲーム批評になってしまうからです。
 項目をつけて、言いたい内容を分散させる。
項目をつけて、言いたい内容を分散させる。

見出しと項目をつけることで、言いたいことを分散させています。これは、読み手にとっても読みやすいし、書き手にとっても書きやすい(まとめやすい)方法なんですよね。
項目の順番は、「ゲーム全体のこと」?「細かい各論」という流れで、「最後に総論」というパターンが多いですね。各論からだと題材であるゲームを知らない人にとってはチンプンカンプン。言いたいことを言うだけでは人には伝わりません。
大切なのは、「どう興味を引かせて、どう伝えるか」。ウチのブログでは、フロントページで今回紹介するゲームについて大層ミステリアス気味に語り、中のページでその解答編を展開するという感じです。
 「面白い」を伝えるのに、何を書くか?
「面白い」を伝えるのに、何を書くか?

ゲームの面白さを伝えるのは、実は非常に難しいことです。なぜなら、「面白い」という感覚は人によって程度も違ければ、ポイントも異なるから。その面白さをどう伝えるかはオリジナリティを出しやすいので、難しい反面、ウデの見せ所でもあります。
(例)GC版バイオハザードの場合
ゾンビは動きも緩慢だし、初期の装備であるベレッタでも数発で倒すことができる。初めは曲がり角の先に急に現れるといったハプニングで驚くこともあるが、慣れればどうとでも対処できる。しかしそれは冷静であれば…の話だ。恐怖は、周囲に気をくばり、集中力を分散させる。恐怖は、必要以上に筋肉をこわばらせる。恐怖は、何より冷静さをどこまでも貪る。GCのグラフィック能力で描かれる洋館は、暗く、闇が濃く、そしてMAP変更に伴った得体の知れなさが甦った。まさに、『そこを歩く恐怖』がここにはある。この新しいステージで自分はいつも通りの対応ができるのか。先々の戦闘に向けて弾数は足りるのか。恐怖は不安を煽り、ふくれあがる不安は内なる敵となる。そのギリギリを一歩一歩歩んでいく様こそ、サバイバルホラー!これこそ、『バイオハザード』の醍醐味といえよう。
 キャッチコピーを考える。
キャッチコピーを考える。

自分が書いた内容を踏まえて、「ちょっとフツウじゃない言い方」あたりを狙って書きます。
×…『グーニーズ』、コナミの名作アクションゲームを再評価する
○…『グーニーズ』、これこそ、コナミ版20世紀少年だ!
ざっと、こんな感じです。それではまた!
DSTT 通販ps3 jbPR














![[PR]](http://bfile.shinobi.jp/6233/cci.gif)
