Comments
Trackback
Trackback for this entry:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |













[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
![[PR]](http://bfile.shinobi.jp/6233/cci.gif)

自らの命をも危険にさらす兵器でしか、この平和は取り戻せない。
レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士だ。
今回発掘した作品は、1987年7月にファミコンで発売された『ボンバーキング』。翌年の1988年には、グラフィックがダウンしたMSX版の存在も確認されている。当時の文献を調べてみると、歴史の古いものの中に『笹川2号』と書かれているものがあり、これが後に『ボンバーキング』と名を変えたらしい。笹川とは本作のメインプログラマーの笹川敏幸氏のことであり、これはいわゆる開発コードネームというもののようだ。
さて本作だが、『ボンバー』という名を冠しているが、名作『ボンバーマン』とストーリー的な繋がりは一切ない。ゲームシステムもまったく異なるもののため、『ボンバーマン』をイメージしてプレイすると大ケガ…もとい大やけどをするので注意が必要だ。
巷では、「クソゲー」とか、「パクリゲー」とか、「ハドソンの黒歴史」とか言われているこの作品。たしかにその一面はあるが、ひと言だけで片付けてしまうにはもったいない魅力があるのも事実だ。
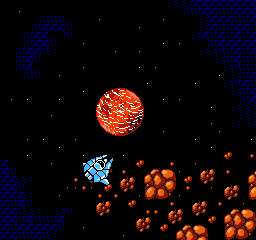
武器もエネルギーも現地調達という、ハダカの王様。![]()
それでは、カンタンに『ボンバーキング』という作品がどんなゲームかを説明しよう。主人公のアンドロイド「ナイト」は、各エリアにおいて障害物を爆弾で破壊しながら進撃し、エリアのゴールを目指す。しかし、舞台は環境制御コンピュータに支配された惑星。ただ進むだけではゴールにはたどり着けない。
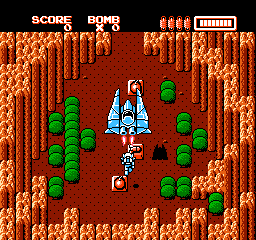
まず必要なのは、ステージ内の障害物に隠された【秘法】。これがないとステージはループし、いつまで経ってもゴールにはたどり着けない。そしてもうひとつ必要なのが【カギ】。これがなければゴールの扉は開かれないのだ。
ナイトの圧倒的不利な立ち位置はまだ終わらない。障害物や敵を倒すために使用する爆弾には使用回数制限がある。最大99個までストックすることができるが、使った分だけ数は減っていく。さらに、ナイトはエネルギーで動いており、ゲージは時間が経過するたびに一定量ずつ減っていく。敵の体当たりや攻撃によってもエネルギーを消費。気を抜けばあっという間にやられてしまう。
惑星アルタイルでの戦いは、基本的に武器もエネルギーも現地調達。敵を倒すか、障害物内に隠れている【エクストラ】パネルを発見することで補給していくしかないのだ。
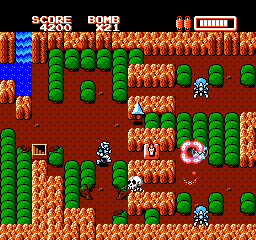
要:危険物取扱責任者資格。![]()
『ボンバーキング』における死亡原因のナンバーワンは、自爆死だ。自分で仕掛けた爆弾の爆風をあびてやられる…という点は『ボンバーマン』と同じだが、本作ではゲームシステムによってより自由になった部分が死亡率をあげてしまっているのだ。
ご存知、『ボンバーマン』は一ブロックおきに破壊不可能なブロックが存在し、ボンバーマンの動きは基本的にタテ?ヨコですむシンプル仕様。しかし、本作ではこの一ブロックおきの破壊不能なブロックがなくなり、ナナメ移動が可能に。ハドソンの開発陣はプレイヤーが自由に動ける範囲が広がった分難易度も上げなければと思ったのか、敵の中には障害物を無視して特攻をかけてくるがデフォルトになった。その結果、爆弾を設置後に「敵をよける」「敵を弾で倒す」といった動作が必要となり、結果、自分の仕掛けた爆発に巻き込まれるという事故が多発してしまうのだ。
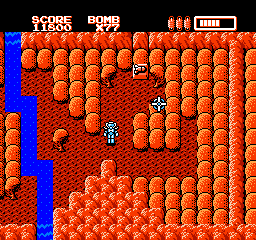
メインテーマのカッコよさよりも、ゲームオーバーの曲のほうが耳にこびりついている…というかつてのファミコン少年少女も多いはずだ。
アイテムを集めて使ってこそのボンバーキングだ!![]()
上記のような理由から『ボンバーキング』はあまり高い評価を得ていない。たしかに難易度は高く、『ボンバーマン』のようなシンプルさはない。しかし、『ボンバーマン』を超えた、王の名にふさわしい派手さは存在する。それが、セクレトできる各種アイテムの存在だ。
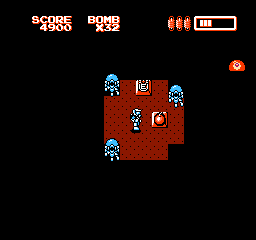
惑星アルタイルには、ナイトの機能をパワーアップさせるさまざまなアイテムが眠っている。一定時間、敵の動きを止める【タイムストップ】、ナイトの速度を速める【スーパーチャージャー】、直線上の障害物をすべて破壊する【ハイパーミサイル】、画面上の敵を全滅させる【フラッシュ】、弾を四方向に撃てる【クロスファイア】、ダンジョンで灯りを灯す【キャンドル】など。
これらのアイテムは、決して出し惜しみしてはいけない。ナイトの通常時の兵装は弱いのだ。だからこそ、「ここぞ!」という時にアイテムはガンガン使わなければとてもクリアはできない。アイテムは、ステージ内の障害物の中に隠されているが、ステージ内に出てくる階段で行けるダンジョンにおいて、かなり余裕をもってゲットすることができる。
だからこそ、使って、使って、使いまくるべし。そうすることでゲームは圧倒的に進めやすくなり、『ボンバーマン』にはない『ボンバーキング』ならではの爽快感?面白さの扉が開かれるのだ。
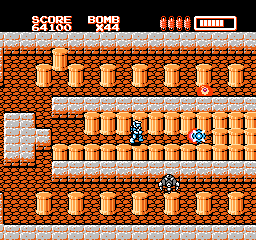
ボンバーマンシリーズに残した大いなる遺産。![]()
視覚?聴覚?触覚に今までない新たな衝撃を与える○超(マルチョウ)シリーズ第一弾と謳われた本作だが、多くのプレイヤーに生まれたのはハドソンへの“殺意”だったのかもしれない。しかし、王が残した遺産は『ボンバーマン』シリーズの新たな進化へと繋がっているのだ。
後に発売されるSFC版の『スーパーボンバーマン』シリーズ、PCエンジンの『ボンバーマン’93』『ボンバーマン’94』では当たり前になっている、ステージごとに異なる世界観を感じられる野外ステージ、あまたの巨大ボスキャラとの戦闘。これらの初出典は他ならない、この『ボンバーキング』である。

王は決して時代から支持された存在ではなかった。しかしその遺伝子は、後世に“素晴らしいモノ”を残したのだ。そのような観点からも、ボンバーマン史はこの作品をなくして語れない。私はそう考えている。
それでは今回の講義は、この歌で締めたいと思う。
