Comments
Trackback
Trackback for this entry:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |













[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
![[PR]](http://bfile.shinobi.jp/6233/cci.gif)
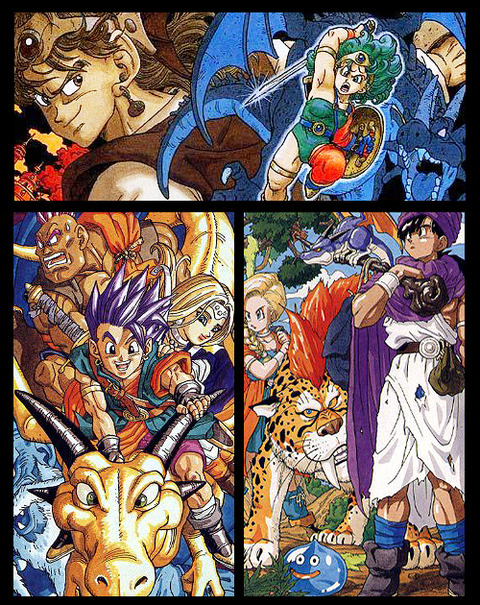
王者の挑戦! RPGの新しいカタチを求め、地平の彼方へ。
今のゲーマー諸君は想像もできないでしょうが、1988年以降のファミコンにはドラクエのパチモンRPGが溢れかえっていました。ナイトガンダムも、ビックリマンも、ドラえもんも、ドラクエ風RPGになっていた時代。それも当たり前です。ユーザーはドラクエのようなRPGを渇望し、作り手には成功するRPGのお手本がドラクエしかなかったのですから。その存在はまさに“カリスマ”でした。
断言します! 『ドラゴンクエスト』がなければ、今日の日のコンシューマRPG文化は存在しません。『ファイナルファンタジー』も、『女神転生』も、『桃太郎伝説』も、『MOTHER』も、『天外魔境』も生まれなかったでしょう。『ドラゴンクエスト』の偉業とは、それだけ大きなものだったのです。
しかし、大きな成功は同時に大きな不幸のはじまりでもありました。『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』によって役目を終えたはずのシリーズでしたが、その人気の大きさゆえに、もう自らの手で幕を下ろすことができなくなっていたのです。「RPGの面白さを伝える伝導師」は、今や「国産RPGの最先端をいく王者」に 。そして堀井雄二氏は、以降の作品の目的を「国産RPGの新しい可能性を探る挑戦」へとシフトさせていくのです。
ドラゴンクエストIV 導かれし者たち![]()
「勇者よ、目覚めなさい。」
いつもの牧歌的なグラフィック、勇者が主人公といったカモフラージュで「変化の乏しいドラクエ」を装っている本作ですが、実は『III』と真逆のアプローチに挑戦していることにお気づきでしょうか。
『III』は「プレーヤー=主人公」であり、主人公視点で冒険を体験していくという作品です。対する『IV』は 「群集劇」。各章の主役たちはプレーヤーが操作することで従来のドラクエこそスタンスを守っていますが、行なっていることは「さまざまな視点から物語を進行させる」というもの。さらに着目すべき点は、「五章構成の体をなしていますが、四章まではあくまでも本編である五章のプレリュードでしかないこと」です。どういうことか? 一章から四章までは、これまでのドラクエの物語では語ってこなかった「世界が危機に瀕していくプロセス」が描かれ、さらに複数主人公の視点を使うことにより、世界で起こっているさまざまなドラマをプレーヤーに見せていく…。つまり、「主人公の冒険を追体験させるゲーム」ではなく、「物語を見せるゲーム」という変質を遂げているのです。
賢明なる読者の方々ならもうお気づきではないでしょうか。「物語を見せるRPG」─―、それは今日のJRPGのスタンスそのものであること。後にライバルとなるファイナルファンタジーが群集劇の手法をとる『ファイナルファンタジーVI』の発売が1994年。本作が発表されたのは、その4年前の1990年です。
本作の魅力のひとつは、主人公が二人いること。プレーヤーが操作できない影の主人公とは、魔物の皇子であるデスピサロです。
彼は、最初名前しか出てきませんが、物語が進むにつれて何かとてつもない禍々しいことを画策している存在であることが分かってきます。そして、さらにストーリーを進めると、一人の美しいエルフを守るために人間を憎んでいるという一面も。そう、デスピサロは勇者の前に立ちはだかるただの悪の大魔王ではないのです。天空の勇者と正反対に位置する、まるでコインの表と裏のような存在。もっとも対極にいるはずなのに、その存在がなければお互いが存在するはできない。特別な使命を帯びていること、愛する女性がエルフであること、心を許した仲間がいることなど、主人公と数多くの共通点も見られます。
それだけに、親友(ピサロナイト)を亡くし、優秀な手駒を失い、切り札である地獄の帝王も倒され、信じていた部下に裏切られ、最愛の人ロザリーを目の前で殺され、心が壊れていく様は涙なくして見ることができません。見た目とうらはらに、『ドラゴンクエストIV』はどこまでも画期的な作品だったのです。
ドラゴンクエストV 天空の花嫁![]()
「強き心は、時をこえて。」
冒険の達成感とは何によって生まれるのだろうか? 「与えられたマップの、行っていない場所を埋めていく」。かつてドラクエ自身が示した方向性は今や既製RPGの常識となっていました。“その先”とはどんなカタチになるのか。『ドラゴンクエストV』が出した答えは、世代?年月という概念を取り入れた「親子三代による壮大な冒険」でした。
マップを広くしても、新しい街を増やしても、ゲームのプレイ時間を伸ばすだけに他なりません。冒険の達成感を味あわせるには旅に費やしたある程度の時間が必要。しかしそれは、プレイ時間である必要はない。そこで、『ドラゴンクエストV』が行なったのは、物語に時間の概念を取り入れるということ。父親の代からずっと続いている旅は、主人公が父の意志を継ぎ、そして家庭を持つ頃に終わりを告げる。これにより、約30時間のプレイ時間で、“数十年にわたる、グランバニアの誇り高き戦士たちの探求の旅”を表現したのです。
前作『IV』は物語性を追求するあまり、マップ上にある町や洞窟の数が増加。そのため、少し歩けば次の町がある…という弊害がありました。それを受けて本作は、作品のテーマである「流浪の旅」を表すため、街の数を減少させることに。しかし、ボリュームがダウンしたわけではありません。同じマップ、同じ街でも、年月が経過すればそこは以前とは全く違う場所。事実、本作ではゲーム中に何度も訪れることになる街がいくつか存在するのが、年月とともにその顔つきはまるで変わっていく。フィールドも同様です。幼少期に父に置いていかれまいと一生懸命に歩いた道、青年期に幼馴染の女の子を探して歩いた道、そして今、子供たちと再び同じ道を歩む。世代?年月という要素が加わることで、「街に行く」、「平野を歩く」という一連の行動にも深みが出たのでした。
余談になりますが、主人公が幼少時に過ごしたサンタローズの村は、青年期になってから訪れるとマップがビミョウに狭くなっています。これは、子供の頃によく行った場所に大人になってから行くと「あれ、こんなに狭かったっけ?」と感じる、あの感覚を再現したそうです。本作にはこのような、実に堀井雄二氏らしい細かい演出がいたるところに散りばめられています。例えば、ゲームスタート時に最初に立ち寄る港。父?パパスは「危ないから外には出るな」と注意しますが、港の外に出ることが可能です。そして、魔物とのエンカウント。どう考えても幼少期の主人公がスライム三匹を相手にするのは難しい。すると2ターン目に、「なんと パパスが かけつけてきた!」とパパスが戦闘に加わります。あっという間にスライムを倒す親子。戦闘終了後、パパスは主人公がどんなにケガをしていなくても「大丈夫か?」とホイミをかけてくれます。これだけのことで、「主人公と父親の関係」を、そして「パパスがいかに主人公を息子として愛しているか」を表現した素晴らしい演出を、私は他のRPGで見たことがありません。
人生とは、よく旅に例えられます。さまざまな人と出会い、別れ、そして前に進んでいく。本作から取り入られた「魔物を仲間にできる」というシステムによるパーティ編成は、奇しくも人生の縮図を感じさせるものになりました。システム自体は『女神転生』シリーズで使われているなど真新しいものではありませんでしたが、鳥山明先生が描く、可愛らしく格好いいモンスターたちとのにぎやかな旅の様子は本作ならではのもの。そのイメージは『ポケットモンスター』誕生のキッカケにもなったと聞きます。
見ず知らずの魔物たちと心を通わせ、馬車は次第に仲間たちであふれていく…。中には、戦力的には二軍だが愛着があって手放せないというキャラもいるでしょう。そう、それこそが『ドラゴンクエストV』の真骨頂。主人公が旅を通して作って行くのは、殺戮兵団ではなく、“家族”なのです。あなたにとってドラクエVはどんなゲームですか?と聞かれたら私はこう答えるでしょう。
人生…かな(笑)。
ドラゴンクエストVI 幻の大地![]()
「この旅は、夢という真実へ。」
『ドラゴンクエストV』は、日本産RPGらしく、物語とメッセージ性の高い優れた作品ではありましたが、正当な評価を受けませんでした。ドラクエが何年も制作期間を設けている間に、市場では新しいRPGの新風が吹き始め、すでにドラクエのスタイルは古いものとなっていたからです。
そして、迎えた『ドラゴンクエストVI』は、「時代の流れを掴まなければならない」という商業的思惑と、「ドラクエはドラクエの道を進む」という信念を両立させるという大きな課題を抱えていたのです。並みのクリエイターならユーザーの意志を尊重した凡作を作ってお茶を濁すところ。しかし、堀井雄二氏率いる制作陣は違いました。過去最大の危機と逆境をはねのけて、過去最高の作品を作り上げたのです。結論から言いましょう! 『ドラゴンクエストVI』はシリーズ最高傑作です。
本作が発売されたのは1995年。「頑張れば誰だって幸せになれる」といった神話はバブル景気とともに崩れ去り、人々はアイデンティティの確立に大いに迷っていました。そんな時代の影響を受けた本作の冒険の目的は、 「魔王を倒す」ではなく「本当の自分を探す」。それは、心の内面にスポットを当てるという新たな可能性の開拓となったのです。
本作では、フィールドマップは二つ存在します。一つは「現実世界」、もう一つは「夢の世界」。夢の世界とは世界中の人々の夢が合わさってできたもの。言い換えれば、“精神世界”です。本来ならば、見ることも触れることもできない世界ですが、主人公たちは元々夢の世界の住人でありながら、現実世界にはじき出された存在ゆえに二つの世界を行き来できる特殊な能力を持ちます。自分たちは現実世界で誰かが夢見ている“こんな風になりたい自分”。ドラクエVIは“夢”が“本当の自分”を探しに行く物語なのです。現実の自分を知っても今よりもいいことなんて何一つありません。現実と向き合うという辛い瞬間が待っているだけ。しかし、“今”と向き合わなければ、先には進めない。先に進むためには心の痛みを伴う通過儀礼が必要であることを主張します。 ドラクエは子供向けのRPG? ハッ、笑わせてくれます。そう感じるのはプレイしている側が幼いだけ。ドラクエVIのストーリーは、ナイフのような鋭さをもってプレーヤーに問いかけてくるのです、「お前の生き方は、本当にそれでいいのか?」と。
主人公が旅先で遭遇するイベントも一筋縄のものはありません。恋人を裏切ったことを後悔し続ける老婆、村を助けてもらった英雄を今度は疎ましく思う人々、たった一回約束を破ったことで人生を台無しにした男、自分の愛のために相手に粘着する魔法使い、甘い言葉につられて楽な道に逃げる人々、強さを求めるあまり孤独に心を蝕まれていく剣士…。30を超えた今、ゲーム中に出てくる人々をとても他人とは思えません。それらは、自分のすぐ近く、知り合いや親戚、友人が陥っているさまざまな人生そのものだからです。
その一方で、本作は「ドラクエの不文律」と思われていることをことごとく破壊しています。「勇者は誰でもなれる」、「魔王は4匹存在する」、「フィールド上に階段がある」、「あえて触れない仲間の過去」、「謎はすべて明かされない」…など。ここには、RPGはもっと自由でいいんだというメッセージが込められているような気がします。
大人がプレイしてこそ真価を発揮するRPG、それが『ドラゴンクエストVI』です。自分の内面と向き合ってもう一度プレイしてみてください。エンディングで孵る卵の中に、あなたは何を見るでしょうか。
